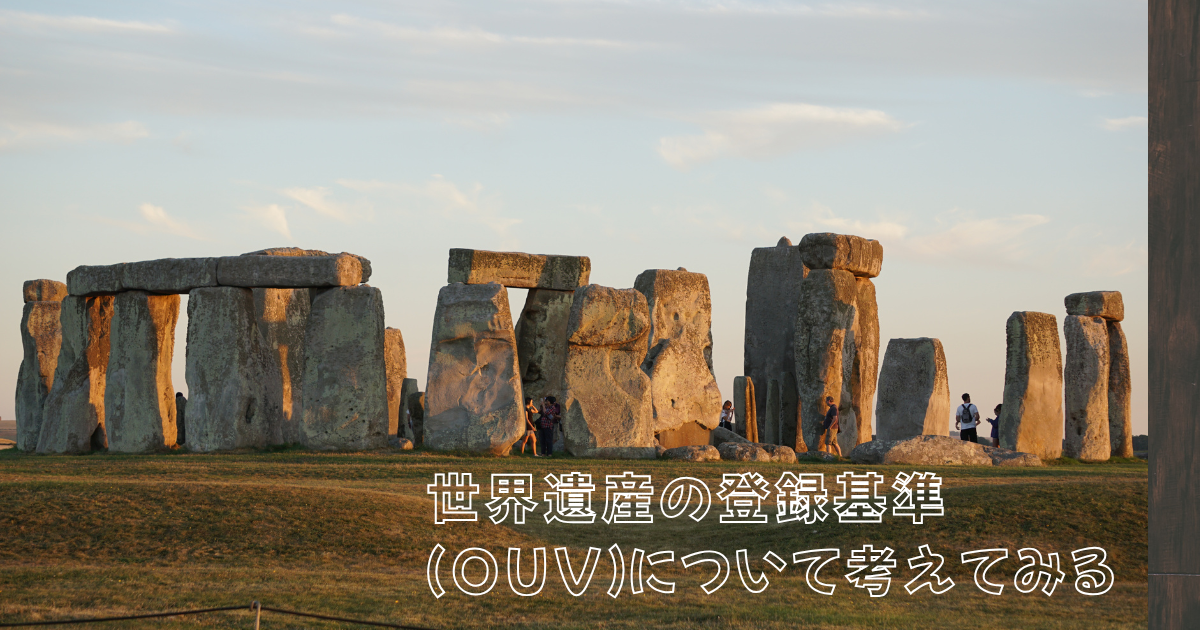
世界遺産登録されるためには、たくさんの審査を受けなければならないのですが、その中に真正性(本物かどうか)という事や、完全性といったものがありました。
世界遺産が持つ顕著な普遍的価値を守るために、必要な要素が完全に揃っているかどうかといったことです。
今回は、その顕著な普遍的価値ってどういうものか、見ていきたいと思います。
世界遺産の持っている価値、顕著な普遍的価値とは
誰もが素晴らしいと思う場所は?と聞かれたら何を思い浮かべますか?
顕著な=素晴らしい
普遍的=すべてのものに当てはまる、時代や場所を超えて変わらず思えること
英語ではOutstanding Universal Value
略してOUVです。
世界中のどの時代や文化の人が見ても、同じように、素晴らしいと思えるのが、顕著な普遍的価値です。
私が見ても、夫や家族、友人やアメリカ人や次の世代の人が見ても、誰が見ても同じ様に、「あ~これってすごいなぁ」ということです。
なるほど、さすがは世界遺産だ。
それだけの価値はあるよね。と思う所はどんな所でしょうか。
人によって様々かも知れません。
私と夫や子どもたちは、趣味も違うし好みも違います。
私は、ヨーロッパに興味があるけれど、夫は自然に興味がある。
ヨーロッパ遺産とアメリカの遺産、アジアの遺産があった時、私が素晴らしいと思うように、ヨーロッパの人たちやアジアの人たちも同じように素晴らしいと思ってくれているのかなって考えると、そうとは言えないかもしれません。
そんな誰もが同じ素晴らしいものだと価値があるんだよというのが、世界遺産の考え方。
その「顕著な普遍的価値」を証明するために、10個の登録基準があるんです。
登録基準「世界遺産条約履行のための作業指針」に記載されている内容の中で、10個の登録基準が定められています。
その中にある登録基準のどれか1つ以上当てはまれば、世界遺産になることができます。
この登録基準のどれか1つが認められるということは、誰もが同じように感じる価値なんだということになるので、それ以外が納得できなくても、この1つにおいては誰もが納得する部分として考えられるということです。
だからそれが世界遺産としての「顕著な普遍的価値」なんですよ。という証明になるのです。
それでは、登録基準10項目を見ていきたいと思います。
世界遺産の登録基準(OUV)10項目
登録基準(ⅰ)人類の創造的資質を示す遺産
登録基準(ⅱ)文化交流を証明する遺産
登録基準(ⅲ)文明や時代の証拠を示す遺産
登録基準(ⅳ)建築技術や科学技術の発展を証明する遺産
登録基準(ⅴ)独自の伝統的集落や、人類と環境の交流を示す遺産
登録基準(ⅵ)人類の歴史上の出来事や伝統、宗教、芸術と関係する遺産
登録基準(ⅶ)自然美や景観美、独特な自然現象を示す遺産
登録基準(ⅷ)地球の歴史の主要段階を証明する遺産
登録基準(ⅸ)動植物の進化や発展の過程、独自の生態系を示す遺産
登録基準(ⅹ)絶滅危惧種の生息域で、生物多様性を示す遺産
登録基準について
登録基準(ⅰ)人類の創造的資質を示す遺産
これは世界遺産としては誰もが知っているような、有名な所が多いです。
人間の才能って人間ってすごいもの作ったんだな。という考え方です。
この遺産知ってる、観た事があるといった遺産は登録基準の(ⅰ)になります。
姫路城、厳島神社、ローマの歴史地区、シェーンブルン宮殿と庭園などがあります。
いくつか訪れた場所があるかも知れません。
本当に、人間って凄いものが作れるんだと思う建物ばかりです。
出来ることなら、実際に足を運び、自分の目で確かめて頂きたいです。
どれだけ写真や動画に残しても、その素晴らしさと感動を伝えることはできません。
登録基準(ⅱ)文化交流を証明する遺産
これは、文化の価値観の交流があるということになります。
例えば、日本の法隆寺だとシルクロードを通ってヘレニズム文化のようなものが、法隆寺の宝物として残っていたり、スペインのイベリア半島はキリスト教とイスラム教の文化が歴史的に混ざり合っていたり、フランスのパリのようなものがあります。
日本では、法隆寺や、古都京都、奈良などがあります。
世界から見て日本は文化交流が大きな価値とされている国なんだなということが分かります。
登録基準(ⅲ)文明や時代の証拠を示す遺産
ここにはこういう文明がありましたよ。こういう文化があったんですよ。という文明の証拠が分かるのが登録基準の(ⅲ)です。
例えば、古都京都と古都奈良の文化財ですが、古都京都の文化財は、長い年月の間、政治や文化の中心だったということですが、古都奈良の文化財は、ここには奈良時代という時代があったんだという仏教を通して1つの国があった時代を証明する遺産となります。
日本では、古都奈良の文化財、富士山一信仰の対象と芸術の源泉などがあります。
富士山を見るたび、昔の人たちも、同じ様に富士山を眺め、どんな風に感じていたんだろうと思います。
登録基準(ⅳ)建築技術や科学技術の発展を証明する遺産
これは、厳島神社のように、社殿が海の上に建てられたりと建築・科学技術の発展を証明するものです。
科学技術としては、ビキニ環礁核実験が行われたことでこちらは負の遺産として時代のパラダイムが動いたということを証明するものとして認められています。
日本では、厳島神社、富岡製糸場、佐渡の金山などがあります。
厳島神社には、子どもの頃に1度訪れましたが、もう一度登録基準という視点から見てみたいです。
登録基準(ⅴ)独自の伝統的集落や、人類と環境の交流を示す遺産
登録基準の(ⅴ)は、伝統的集落、人類の環境の交流です。
独自の集落が残されているものとして、有名なものは、白川郷の合掌作りがあります。
白川郷の合掌作り集落へは、家族と訪れましたが独自の集落で、中に入ると非現実のような感じで自分が昔ばなしの主人公になった気分になりました。
日本では、白川郷・五箇山の合掌造り集落、岩見銀山遺跡とその文化的景観や北海道・北東北の縄文遺跡群があります。
登録基準(ⅵ)人類の歴史上の出来事や伝統、宗教、芸術と関係する遺産
こちらは、人類の出来事や伝統、日本の独自の宗教体系や考え方というものが世界から評価されている遺産になります。
日本の世界遺産で登録基準(ⅵ)として認められているものは、全部で10件。
法隆寺地域の仏教建造物だったり、厳島神社や日光の社寺などがあります。
また、世界遺産には、戦争や人種差別など人類が歴史上犯してきた過ちを2度と繰り返さないように教訓として、負の遺産と呼ばれるものがあります。
広島の平和記念碑やゴレ島などは、「負の遺産」として、(ⅵ)のみで登録されています。
この(ⅰ)から(ⅵ)までが文化遺産の登録基準になります。
登録基準(ⅶ)自然美や景観美、独特な自然現象を示す遺産
ここからが、自然遺産の登録基準になります。
(ⅶ)は、自然美や自然現象です。
地球って美しいなと分かるものがこれですが、こちらも文化遺産の(ⅰ)と同じように、有名な観光名所だったりします。
日本では、屋久島が唯一認められている世界遺産です。
登録基準(ⅷ)地球の歴史の主要段階を証明する遺産
(ⅷ)は、この美しい自然がどうやって出来たかという地球の歴史が分かるものです。
例えば、ハワイ火山国立公園です。
火山が起こって、海に流れ込み新たに島が出来ていくといった今まさに、地球が変化していってるんだというのが(ⅷ)になります。
日本ではこの(ⅷ)はありません。
登録基準(ⅸ)動植物の進化や発展の過程、独自の生態系を示す遺産
(ⅸ)(ⅹ)は生物や生態系に関する自然遺産になります。
(ⅸ)は、動物の進化や発展が分かる独自の生態系が見られるもの。
日本では、白神山地のブナの原生林、屋久島や知床など。
オーストラリアのグレートバリアリーフのような、その地域でしか見られない生態系があるのが(ⅸ)になります。
屋久島には是非訪れてみたいです。
登録基準(ⅹ)絶滅危惧種の生息域で、生物多様性を示す遺産
最後は、生物の発展過程で生物の多様性が見られる、絶滅危惧種がいます、というのが登録基準の(ⅹ)になります。
日本では、知床、奄美大島、徳之島、沖縄県北部及び西表島があります。
自然遺産では、(ⅶ)(ⅷ)が地球に関するもの
(ⅸ)(ⅹ)が生物や生態系に関する地球環境になります。
この登録基準を覚えておくと、世界遺産をみた時に、(ⅲ)だから、文明の証拠としてこれがあるんだなとか、見るポイントとして分かりやすくなって、より深く知る事が出来て、嬉しくなります。
私も世界遺産を訪れる際は、そういった点を見るようにします。
次回から、どんなものが世界遺産に登録されているのかを見ていきたいと思います。
前回の記事はこちら☟
参考にさせて頂いたもの


