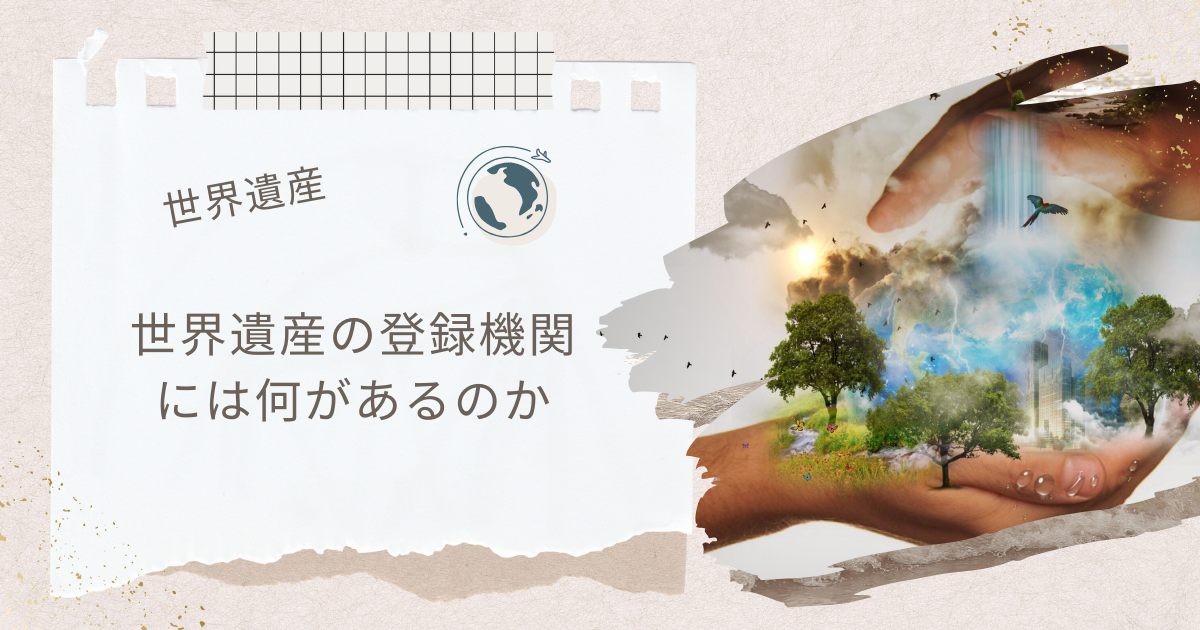
世界遺産というのは、最初どうやってその遺産たちが守られてきたのかという所から考えていきますが、その流れには必ず関連する機関というものがあります。
今回はその世界遺産に関係する機関には何があるのかを見ていきたいと思います。
世界遺産の登録機関には何があるのか
世界遺産委員会
世界遺産に関係する機関としては、まず世界遺産委員会というものがあります。
世界遺産委員会は、世界遺産条約の締約国の21か国で構成されています。
通常は1年に1回開催されて、任期は6年です。
任期は6年ですが、なるべく4年で交代してくださいとねとなっているようです。
世界遺産委員会は、どんなことをしている機関かというと、有名なのが世界遺産リストへの推薦遺産を登録するかしないかという審議です。
今まではそれしか知らなかった私ですが、この推薦された遺産についても4段階の審議が行われます。
1番が登録。
これは、世界遺産としての、OUV(顕著な普遍的価値)が認められて、世界遺産リストに記載するという決議。
2番目は、情報紹介決議。
これは、世界遺産としての価値OUV(顕著な普遍的価値)は認められるのですが、追加の情報も必要ですよ。という決議。
3番目が、登録延期決議。
これは、世界遺産としてのOUV(顕著な普遍的価値)は認められるのですが、本質的な推薦書の練り直しを求めるものになります。
これを受けると、次の次の年に再度審議を受けるということになります。
そして最後4番目が、不登録決議。
これは、そもそも世界遺産としてのOUV(顕著な普遍的価値)は認めません。なので世界遺産リストには記載しないです。ということでこれが出てしまうと、その遺産は同じ価値として推薦することができなくなってしまいます。
世界遺産委員会は、それ以外にも既に登録された遺産の評価報告を受けたり、モニタリングを行ったりとか、世界遺産基金の使い道であったりと多くのことをやっている機関になります。
色んな事をやっている機関なので、ついつい自国優先になったりしがちです。
任期を4年にしてくださいねという理由は、わかる気がします。
世界遺産センター
世界遺産センターは、1992年に設立されました。
何をする機関かというと、世界遺産委員会の事務局を担う機関になります。
パリのユネスコ本部に常設されており、推薦書は基本この世界遺産センターに提出し、世界遺産センターがイコモスに調査を依頼したり、取りまとめを行ったりしています。
ICOMOS(イコモス)
1965年に設立された国際記念物遺跡会議と呼ばれるもので、パリに本部を置くNGOになります。
こちらは、ベネチア憲章の原則を基に、建物や考古学的遺産の価値そのものの保護などを行います。
「真正性」と呼ばれる建物の景観や文化的背景や独自性がしっかりとなされているか確認するところです。
本物かどうか?を確認する機関ですね。
世界遺産委員会に諮問機関として会議に参加したり、事前評価なども行う文化遺産に関する専門家集団になります。
IUCN(アイユーシーエヌ)
IUCNは、国際自然保護連合で1948年に設立されました。
スイスのグランに本部を置き、ユネスコやフランス政府、スイス自然保護連盟などが中心となって立ち上がったものです。
こちらは、自然の多様性の保護や持続可能な自然資源の利用を行うために、自然遺産の諮問機関として世界遺産委員会に参加します。
ICCROM(イクロム)
文化財の保存及び修復の研究のための国際センターになります。
イタリアのローマに本部が置かれ、技術者や専門家の援助を行ったり不動産だけではなく動産の保護両方の文化遺産の保全教科を目的とした研究や助言を行っています。
まとめるとこんな感じです。
世界遺産委員会➡21か国で構成。任期6年 世界遺産委員会委員国の選定
世界遺産センター➡世界遺産委員会の事務局
イコモス➡文化遺産の事前調査・文化遺産に関する専門家集団
IUCN➡自然遺産の事前調査・自然遺産に関する専門家集団
イクロム➡不動や動産の保護
こうやって沢山の機関が長い年月をかけて調査し、世界遺産として登録されていくのですね。
次回は世界遺産に関係するキーワードと世界遺産の登録基準についてみていきます。
前回の記事はこちら☟
基本から知りたいという方におすすめ
