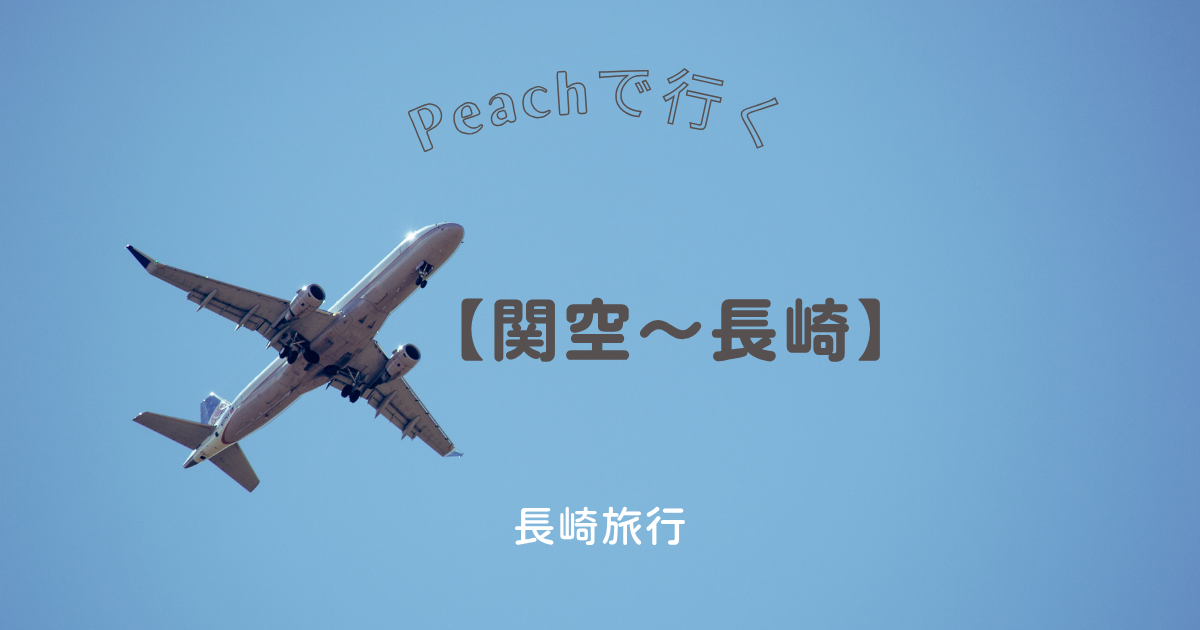世界遺産を学びながら夫婦でいく2泊3日の長崎の旅。
今回は世界遺産で注目される人気エリアの1つ、グラバー園を訪れた感想です。
世界遺産を歩く【グラバー園】入園料

大浦天主堂を訪れた後はグラバー園へ。
(大人1人620円)。
途中「角煮まんじゅうを是非食べて欲しい!!」と修学旅行で訪れたことがある子ども達からのおすすめで、1つ購入。(590円)
ホカホカの角煮まんじゅうは、皮がほんのり甘く、また甘辛く味付けされた角煮がジューシーでお昼ご飯を食べ損ねていたことも重なって、とても美味しかったです。
グラバー園内ツアー(無料)
園内の見どころをガイドが案内してくれます。
こちらの園内ツアーを利用したかったのですが間に合いませんでした(残念)。
旧三菱第2ドックハウススタート
所要時間:60分
予約:不要
料金:無料
時間:11:00~、13時~、15時~
休み:無休
大浦天主堂の記事はこちら☟
【グラバー園】所要時間
大浦天主堂からグラバー園までは徒歩約6分。
園内をじっくり周って約1時間でした。
旧グラバー邸
トーマス・ブレーク・グラバーが1863年に建てた住居。
グラバー園といえば、こちらが一番有名な住宅です。
スコットランド出身の商人トーマス・グラバーは、蒸気船の普及にともなう石炭需要の増大を見込み、佐賀藩とともに高島炭鉱を長崎に開発しました。
そんなグラバー氏が家族と過ごした住宅。
コロニアルスタイルのベランダに漆喰塗の壁。
部屋に飾られてある食器はどれもおしゃれ。
ベッドカバーには、和柄のシーツを取り入れられた和洋折衷の部屋でとても可愛らしい印象でした。

その他に旧グラバー住宅、旧ウォーカー住宅や旧リンガー住宅、旧オルト住宅とあります。
残念ながら旧オルト住宅が工事中のため見学できませんでしたが、どの住宅も可愛らしく、各部屋はメルヘンチックで、当時の生活の様子を想像すると、まるで絵本の中にいるような気分になりました。
グラバー園は、2015年「明治日本の産業革命遺産」の構成資産の1つとして世界文化遺産にも入っています。
この日は、修学旅行で訪れていた小学生たちがいて、とても賑やかでした。
私が感じるグラバー園と彼らが感じるグラバー園とでは、感じ方が全く違うだろうけれど、世界遺産に興味を持った子が何人かいるのだろうなと思うと嬉しいです。
歩きながら長崎港を見下ろす美しい景色や色とりどりの花が咲く庭園には、レトロなカフェやレンタルドレスもありました。
若い頃は素敵なドレスを着たくなったものですが、この歳になると、ドレスよりも動きやすい服や靴が気になるところです。
ハートを探そう
園内の石畳の中にハート型の敷石(ハートストーン)が埋め込まれています。
ハートの石を見つけて、ハートストーンに触れると(恋)の夢が叶う?らしい。
夫婦2人で頑張って、探しました。
最後の1つが分かりにくかったのですが、3つとも探す事が出来ました。

ハートの石畳:1つ目
グラバー邸を見下ろす階段
ハートの石畳:2つ目
長崎の街を見下ろす場所
ハートの石畳:3つ目
レストハウス横(ガーデンハウス)
今後も夫婦で旅行に行きたいので、夢が叶うといいな。
長崎おくんちホール

グラバー園の見学後に、長崎おくんちホール(長崎伝統芸能館)があり、長崎くんちに奉納される曳物などが展示されてありました。
この日は長崎くんち最終日で、長崎タウンではお祭り真っ只中でした。
ガーデンショップ

ガーデンショップではグラバー園のおみやげを購入できます。
私は昔懐かしいドロップ缶(385円)を購入。
グラバー園では、ドロップ缶のみでしたがそれ以外の場所でたくさんおみやげを購入してしまいました。
毎回そうですが、旅行に訪れると財布の紐が緩みます。
また園内のガーデンショップでは「世界遺産検定認定証」を提示するとポストカードが1枚プレゼントされるので訪れた際はお気に入りのポストカードをゲットしてください。

グラバー園の後は長崎新地中華街へと向かいます。