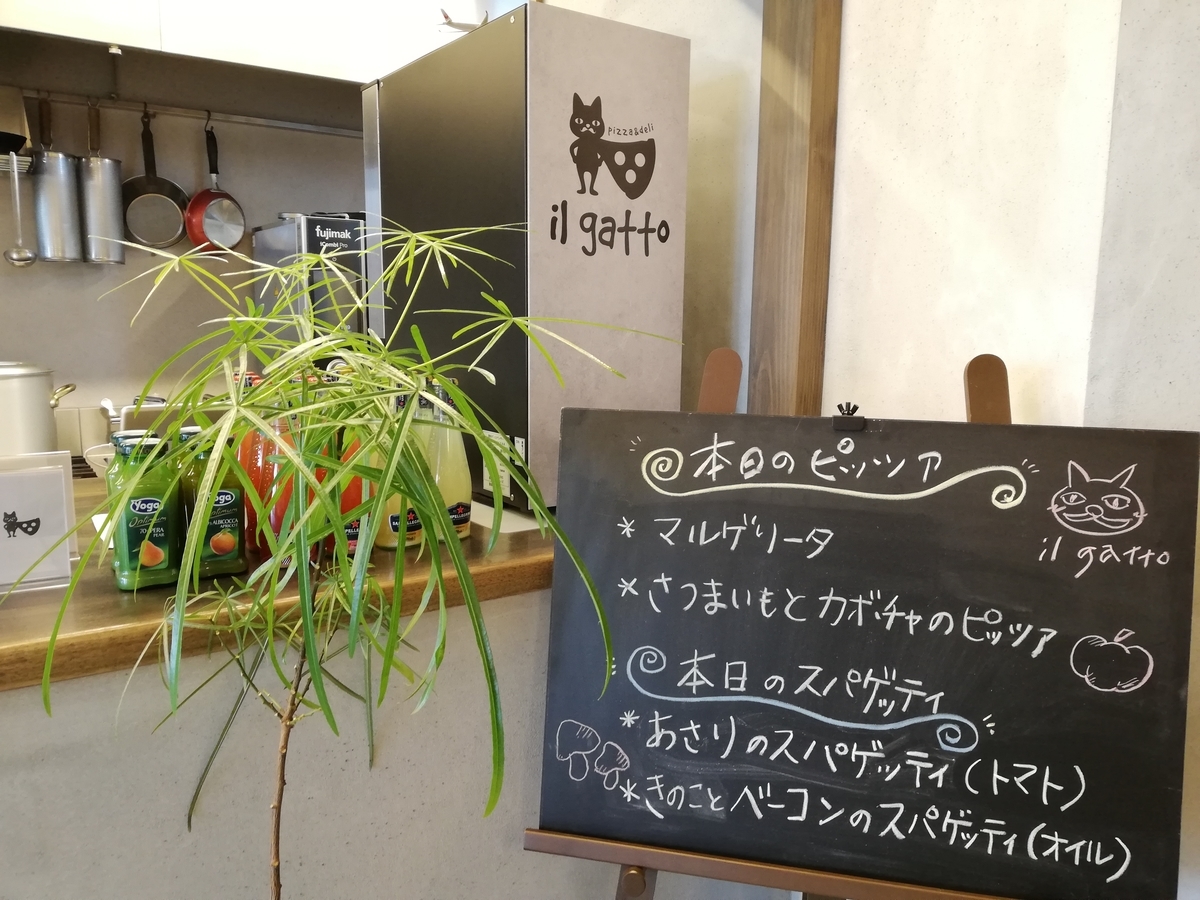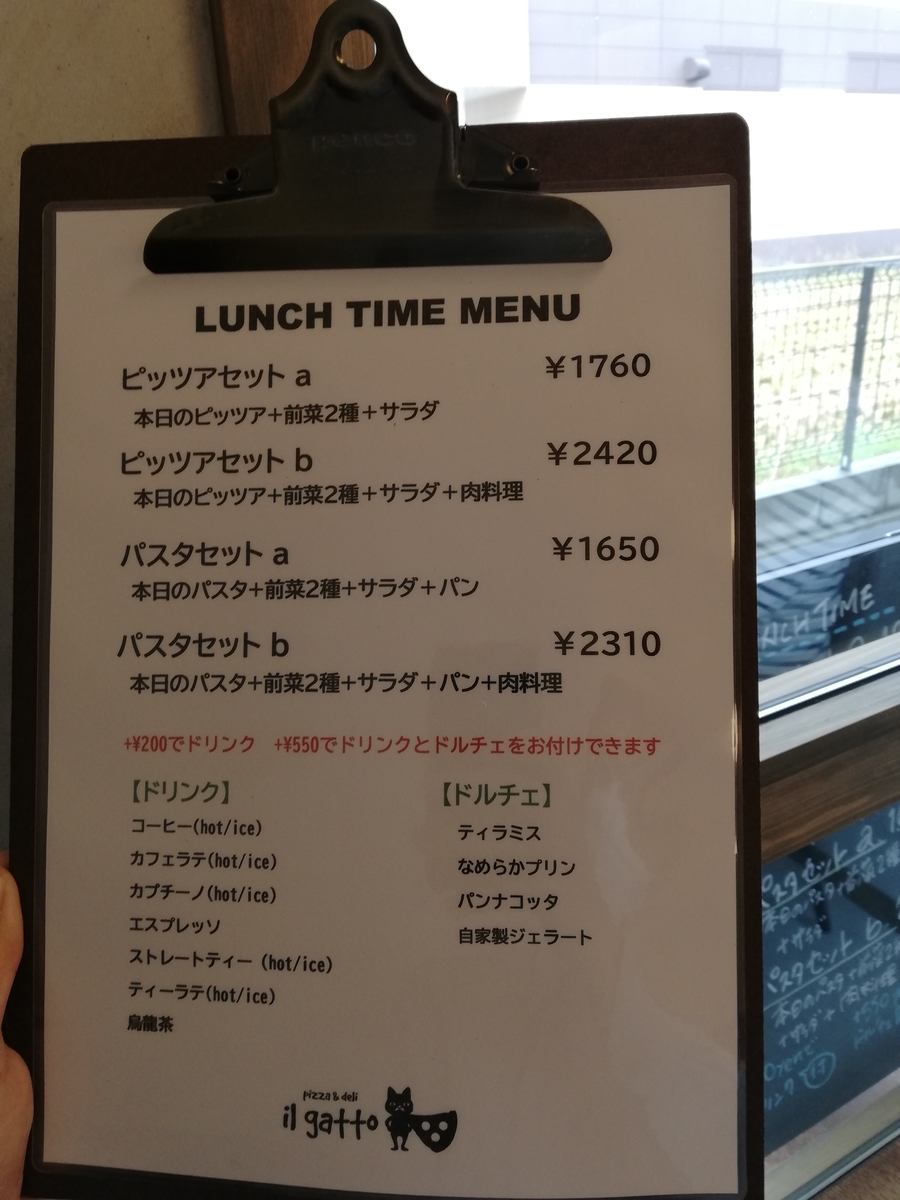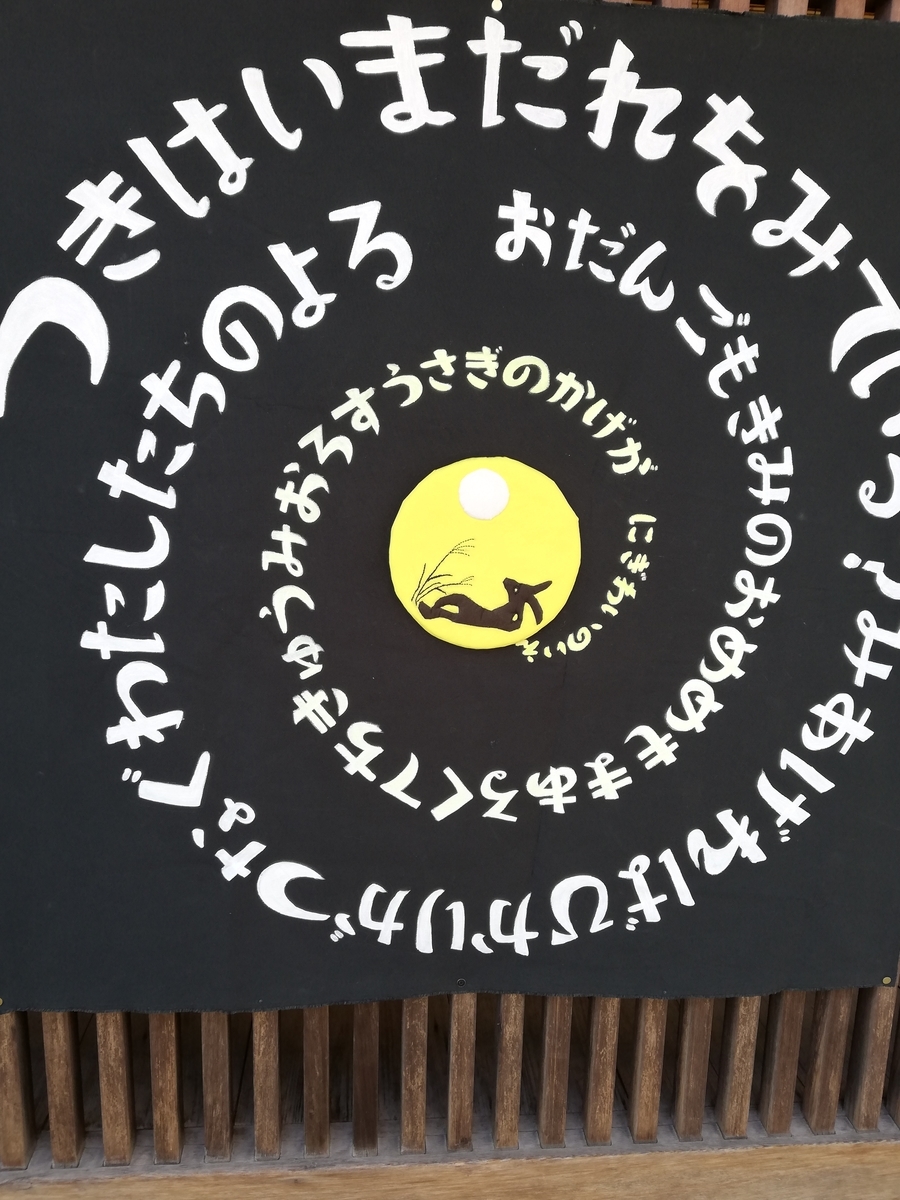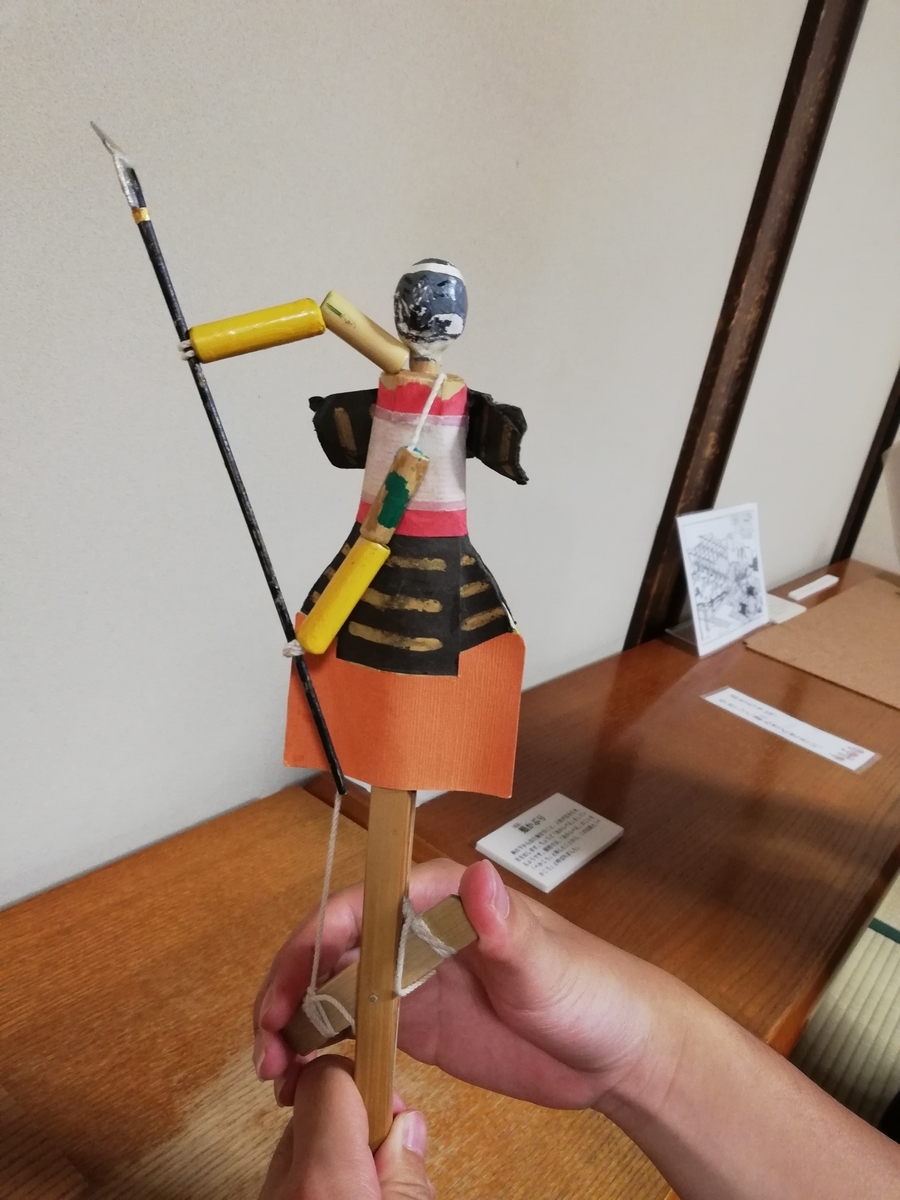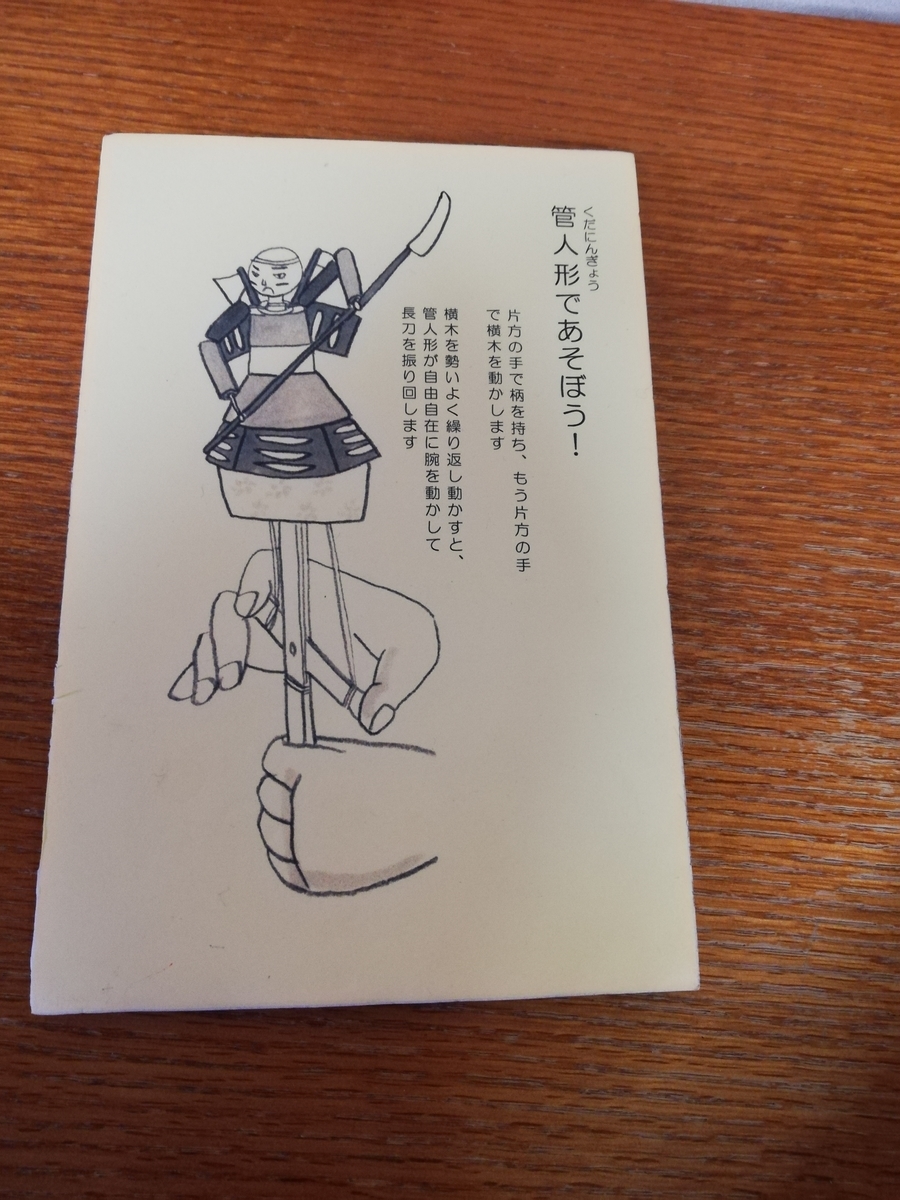ガネしゃんです。いつもご覧頂きありがとうございます。
息子は大学3年生。
この夏インターンに応募、参加し自分なりに色々と考えているようです。
少し古い記事になりますが、毎日新聞の有名人が自身の学校生活を振り返る「学校とわたし」というコーナーで、明治安田生命保険社長が語る「リーガルマインド大切に」という記事があったので、ご紹介したいと思います。
永島 英器(ながしま ひでき)
明治安田生命保険社長
1963年、東京都生まれ。東京大法学部卒。86年に、現・明治安田生命保険に入社。企画部長や人事部長などを経て2021年から現職。プロ野球・阪神タイガースの半世紀にわたるファン。
中学校の社会科見学で地方裁判所に行き、公判を傍聴しました。どんな事件だったのかは、よく覚えてはいませんが、被告の女性は恵まれない境遇で育ち、その背景があった故に罪を犯した人でした。子供心に「善悪とは何か」と考え、困っている人を助ける弁護士になろうと大学で法学を勉強することにしました。
東京大に入学して1,2年間は「法とは何か」を考え、広く教養を身に付ける法哲学の授業が多かった。例えば悪意があるから罰するのか、悪意はなくても結果的に誰かを傷付けたから罰するのかといったテーマについて考えました。話し合う授業が楽しく、のめりこみました。その結果、司法試験に向けた法律の暗記や授業を退屈に感じ、弁護士になるより就職活動をしようかと考えるようになった。
明治生命保険(現在の明治安田生命保険)に入社したのは、OB訪問で会った先輩が楽しい人だったからです。スーツの下に派手なシャツを着ている個性的な人で、自由な会社だと感じました。他人の人生に関わり困った時に手を差し伸べるのは、保険も弁護士と同じだとも思いました。
大学で学んだ法哲学は、今も仕事での判断に生きています。全てを法律などでルール化すれば、社会は安定しやすくなるけれど、単純にルールに当てはめられないことも多くあります。どちらを重視するか、矛盾とどう折り合いをつけるかを考えて、的確な判断を下すことを「リーガルマインド」と呼びます。
人事部長時代、社内結婚で共働きの社員は、なるべく同じ家から通える配属になるよう見直しました。社員の意思にかかわらず転勤があり、女性は寿退社が当たり前だった時代を引きずっていたのです。社長になってからは、介護など家庭の事情で東京にある本社から離れた場所に住む社員も、本社の業務を遠隔で続けられる制度を導入しました。社員1人1人が幸せになれるよう判断したいですね。
今は理系がもてはやされ、「文系は社会に出て役に立つのか」と言う人もいます。でもロボットやAI(人工知能)の時代になればなるほど、社会や人間について再定義を求められ、倫理や哲学が必要ではないでしょうか。若い人に法学部で学んで欲しいと思っています。
文系も社会に出て役に立つ
息子は法学部です。
「法とはなにか」を学んでいくうちに、学ぶ前とでは考え方が変わったそうです。
もともと政治が好きで今も法より政治の方が好きだという息子ですが、法律を学んだことで、政治と社会について深く考え、また言葉の意味にこだわることで、物事を論理的に考え、順序だてて説明出来るようになったと思っています。
偉そうに書いている母ですが、言葉の意味にこだわることで、物事を論理的に考え、順序だてて説明出来る能力が私には不足しています(;・∀・)
法律で勉強する文章は人を説得する目的で記述された文章が多いです。
多くの文章を読み、多くの問題について深く考える事が出来、トラブル対応についても対処できると思っています。
息子の場合は、アルバイトのコンビニでは、様々な人と接す事で人との対応の仕方、効率よく働く方法等、辛かった時期もあったけれど踏ん張って続けた事で今があること。
塾では個別指導、多人数での指導の仕方等、どうすれば勉強に興味を持ってくれるのか?自分なりに日々考える事も多いと思います。
文系・理系だからだけではなく、こういった日々の生活を通して人として日々成長している事は間違いありません。どれだけ真剣に取り組んできたのか?を大切にして下さい。
な~んて考えている母親です。

経験者からのアドバイス
2月に赴任先の中国から一時帰国する私の弟からの息子へのアドバイスです。
息子だけでなく、大学生に是非読んで貰いたいと思うアドバイスなので、ここに記しておきます。
○○君、お疲れ様。早いものでもう11月半ばを過ぎてあっという間に年末ですね。
予定通り2月に一時帰国します。中国に入国時の隔離が以前よりかなり短くなったのはありがたいです。ちなみに○○君も来年は4回生ですね。色んな選択肢があると思いますが、将来を決める大切な時期なので、自分が将来何をしたいのか良く考えて決めて下さい。
~中略~
1番の決め手になったのはOB訪問と人事担当者の話を聞いた事でした。
何をやってる会社とか詳しく聞くとかではなく、この人がいる会社でこの人達となら一緒に働けるかな、みたいな。
まあ、実際に入ってみるとブラックな部分も当然あるし嫌な事もありますが、今となってはこの会社に入って良かったと自信を持って言えます。
ですので、もし一般企業を目指しているならできるだけ多くの会社の人と会ってその人がその会社にどんな魅力を感じてるのか良く観察してみる事をお勧めします。
2月に会った時にまたゆっくり話しましょう。
小さい頃は弟とケンカをしたものですが、大人になり家庭を持った事で互いに思いやる事が出来ている様な気がします。
息子に素敵なアドバイスを有り難うと心から思っています。
Win-Winの関係をめざして~母の願い~
私はWin-Winの関係が好きです。誰かの幸せのために自分を犠牲にしてしまうのは、Win-Winの関係ではありません。
本当に他人のために何かをし続けたいと思っているのであれば、まずは自分を大切にすることが絶対に必用です。自分が犠牲になっておらず、元気な状態であるからこそ、他人のためになる事を継続的にできるようになるのだと思っています。
弟と同じく、子供達には自分を大切にして欲しいです。
そして息子が選ぶ企業が従業員を大事にすることで良質な人材を確保し、それによってサービスの質を上げて好業績を達成していく事を私達家族は心から願っています。
アラフィフの私ですが、今後も法について学び続けるので、若い人も法学部で多いに学び一緒に社会をよくしていければと思っています。